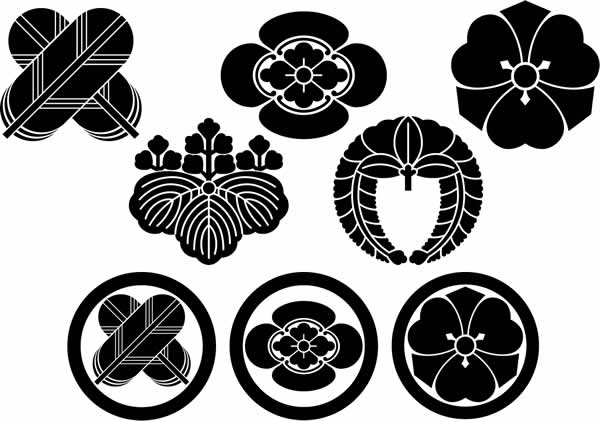実存主義者の哲哲学者・作家であるサルトルの小説「嘔吐」。
結局何が言いたいのかよくわからないサルトルの嘔吐について、あらすじをわかりやすく要約しました。
サルトルの「嘔吐」、超ざっくり要約したわかりやすいあらすじ
物語の舞台は18世紀のフランスのブーヴィルという港町。
主人公である30歳のアントワーヌ・ロカンタンは、旅行家兼歴史研究者であった。
ある日突然、ロカンタンは自分の中の変化に気づいてしまった。
海岸で拾った小石やカフェのウェイターが着けているサスペンダーなど、なんでもないものを見て吐き気をもよおすのだ。
そしてついに自らの手さえも、見ると吐き気をもよおすようになっていまった。
そんな中、公園の樹木であるマロニエの根っこやマンホールの蓋を見て激しい吐き気にみまわれた。
ロカンタンはついに、自分の吐き気の正体が「“もの”が“実存”しているという事実」であることに気づいてしまった。
それからロカンタンの「存在」に対する吐き気は、狂気や自己嫌悪となっていく。
最終的にロカンタンは、世の中のすべて物の存在は無意味であり、抽象的な概念でしかないことに気づくのだった。
以上が、「嘔吐」のかなりざっくりとしたあらすじとなります。
ストーリーそのものは、何か大事件が起きたりするような物語らしいエピソードがあるわけではありません。
「嘔吐」は、サルトルの思想を具現化した作品と言えます。
ジャン=ポール・サルトルとは
「嘔吐」の原作者である「ジャン=ポール・サルトル(Jean-Paul Sartre)」は、実存主義(英:existentialism)の代表的な哲学者であり小説家です。
フランス・パリに生まれ、「嘔吐」「存在と無」「実存主義とは何か」などの作品を執筆しました。
1964年にノーベル文学賞を受賞しましたが、自ら受賞を拒否しました。
実存主義を掲げ、世界各地をまわって講演活動を行いましたが、1980年に亡くなりました。