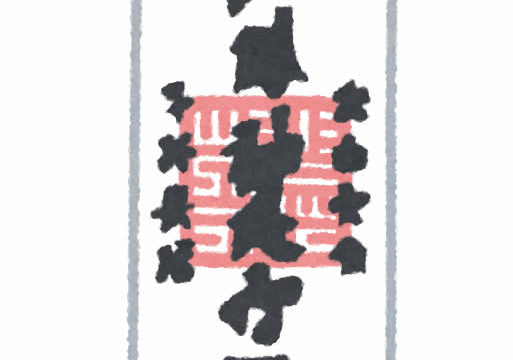新年に神社や寺院に参拝し、一年の平安を神様にお祈りする「初詣」。毎年の恒例行事になっているという人も多いのではないでしょうか。
元旦や三が日に行けなくても、1月中に参拝できればOKという話はよく聞きますが、1月の間でも初詣に行ってはいけない日があるのか気になったことはありませんか?
せっかく初詣に行くなら、適さない日は避けたいですよね。
この記事では、初詣に行ってはいけない日はあるのか、また2023年1月ではその日がいつに当たるのかについてご紹介します。
初詣に行ってはいけない日は?
結論からいうと、この日は絶対に初詣に行ってはいけない!という強い決まりはありません。
ただ、できるだけ避ける方が良いという日はあります。
忌み中(四十九日期間)の日

親族を亡くして喪中である場合、まだ四十九日が過ぎていない忌み中の期間は初詣に行くべきではありません。
四十九日の間はまだ故人が近くにいるという考えから、神様の近くにいくことは良くないとされているからです。
ご自身の家が仏道であればご不幸があってから四十九日間、神道であれば五十日間は、初詣は避けるほうがいいでしょう。
逆に、まだ一年以内である喪中であっても、四十九日を過ぎて忌明けをしているのであれば、初詣に行っても問題ありません。
不成就日(ふじょうじゅび・ふじょうじゅにち)

不成就日(ふじょうじゅび・ふじょうじゅにち)」とは、十干十二支をもとに決められた凶日のこと。
この不成就日に始めたことは何をやっても成就しないとされ、とても縁起が悪い日です。
不成就日は月に数回ありますが、この日に神様にお願いごとをしても、成就しなさそうな気がしてしまいますよね。
気持ちの問題もありますが、できるなら避けた方がいい日とも言えるでしょう。
ちなみに、よく吉日・凶日として使われる「大安」や「仏滅」は「六曜」という考え方ですので、不成就日とは別物です。
そのため、凶日である不成就日と、吉日である大安が重なるということもありえます。
どっちを信じればいいの?と疑問に思ってしまいますが、最終的にはご自身が信じる方で判断するしかありません。どうしても気になってしまう場合は、わざわざ凶日に行かずに他の日を選択するのが無難でしょう。
2023年1月の不成就日
2023年1月の不成就日をご紹介します。初詣のスケジュールを立てる際のご参考にしてください。
- 1月5日(木)
- 1月13日(金)
- 1月21日(土)
- 1月24日(火)
初詣に適した日は?いつまでに行けばいいの?
その年に初めて寺社に参拝することを初詣といいますので、いつが良いとか、いつまでに行かなければならないという決まりはありません。ですから、慌てなくても大丈夫なんです。
とはいえ、気分的にはできるだけ早く参拝したいと思いますよね。
一般的には、初詣に適した日や期間は下記のような目安があります。
三が日中
1月1日の元旦から1月3日までの三が日に行く人が多いです。
三が日はお正月ムードが高まる期間ですし、仕事が休みという人も多いため家族そろって出かけやすいためでしょう。
松の内期間中
一説には「松の内」の期間が終わるまでに初詣にいくのがよいとも言われています。
松の内は家庭や神社に歳神様がいらっしゃる期間ですので、初詣もその間にいくということですね。
松の内の期間は地域によって違いがあります。関東では1月1日~1月7日、関西では1月1日~1月15日となっています。
旧正月を目安にする
旧正月を目安にするという考え方もあります。
旧暦では、1月末から2月初旬ごろが旧正月となり、新年の始まりは立春になります。
2023年の立春は2月4日(土)となりますので、その前後を目安に初詣に行くというのもいいでしょう。
いまでも一部の寺社では旧正月の頃まで正月行事を行っているところもあります。
初詣に適した時間帯はある?避けるべきは?
初詣に行く時間に関しても、とくに決まりはありません。
神社の場合は門がないことが多いですので、どの時間帯でも参拝は可能ですが、極端に遅い時間はおすすめできません。
大晦日から元旦にかけて年越しで初詣をする「二年参り」の場合は、神社や寺院も夜間の参拝を許していますので問題ありませんが、三が日以降であれば深夜の初詣は避けましょう。
逆に午前中の参拝は、神社の空気も澄んでおり良い気を受けることができるとされているため、参拝に適した時間帯といえます。
可能であれば、初詣は午前中に行くのがおすすめです。
まとめ
初詣に行ってはいけない日、また参拝におすすめの時間帯についてご紹介しました。
忌み中・不成就日などに初詣にいったからといって何か罰があるわけではありませんが、できれば気持ちよく参拝したいものですよね。
初詣に行く時のご参考にしていただければ幸いです。